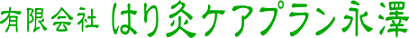四十肩・五十肩は安静にした方がいい?動かした方がいい?どれくらいで治る?(前編)

肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)になると、「動かしたほうがいいの?」「安静にしておいたほうがいいの?」と迷う方が多いです。
実はこの答えは痛みの時期によって違います。
炎症が強いときは無理に動かさず、痛みが落ち着いてきたら少しずつ動かすことが回復への近道です。
ビーボに来所される年齢の方のほとんどが筋力、血流の低下による肩の痛み、可動域が狭くなって腕があがらなくて困っている方だと思います。どんな運動をしたら良いのかわからなかったり、運動する機会がない方に合わせて機能訓練指導員が丁寧にご指導させていただいております。しかし、その前に御自分やご家族の方が四十肩・五十肩について知ってもらうことで予後が大きく変わるのでぜひ今回のブログを御覧ください。
目次
- 四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)はどうしてなるの?
- 四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)はどうして痛いの?
- 四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)はどんな事に困るの?
- 四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)は安静にした方がいいの?動かした方がいいの?
- 四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)【前編】まとめ
1. 四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)はどうしてなるの?

四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)はどうしてなってしまうのでしょうか?
- 加齢や使いすぎによる組織の変性
- 血流の低下
1. 加齢や使いすぎによる組織の変性
年齢を重ねると、腱や靭帯、関節包の柔軟性が低下します。これにより、小さな傷や炎症が起きやすくなります。特に「上腕二頭筋長頭腱」や「棘上筋腱」の周囲がダメージを受けやすいです。
2. 血流の低下
肩関節の周囲(特に関節包や腱)はもともと血流が少ない組織です。年齢や姿勢(猫背など)によって血流がさらに悪くなり、修復力が落ちて炎症が長引くことがあります。
2. 四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)はどうして痛いの?

四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)はなぜ痛いのでしょうか?痛みの原因はいったいなんなのでしょうか
- 炎症そのものによる痛み
- 関節包が硬くなって引っ張られる痛み
- 二次的な筋肉の緊張
1. 炎症そのものによる痛み
関節包や腱板、滑液包などに炎症が起こると、炎症物質(プロスタグランジンなど)が出て、 神経を刺激します。これが「ズキズキ」「ジーン」とした安静時痛(夜間痛)になります。
2. 関節包が硬くなって引っ張られる痛み
炎症が続くと、関節包が縮んで厚く・硬くなります(拘縮)。この状態で腕を動かすと、包みの膜が引っ張られて「ビーン」と痛みが走ります。 → これが「動かすと痛い」「上がらない」痛みです。
3. 二次的な筋肉の緊張
痛みで動かさない期間が長くなると、肩まわりの筋肉(特に三角筋や僧帽筋など)がこわばって血流が悪化します。これも「鈍い重だるさ」や「肩こり感」として痛みを強めます。
3. 四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)はどんな事に困るの?

四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)になってしまうとどんな事にこまるのでしょうか
- 日常生活での動作が痛い・できない
- 夜間の痛み・睡眠障害
- 動かさないことによる悪化
- 心理的・社会的な困りごと
1. 日常生活での動作が痛い・できない
上にあげる動作が痛い
- 髪をとかす
- 洗濯物を干す
- 高いところの物を取る
➡️ 肩を「外転」「屈曲」させる動作が制限されるため。
後ろに回す動作が痛い
- 下着のホックをとめる
- ズボンの後ろポケットに手を入れる
- エプロンのひもを結ぶ
➡️ 肩の「内旋」「伸展」が制限されるため。
横や前の動きでも支障
- 着替え(シャツを脱ぐ・袖を通す)
- 料理や掃除など、腕を使う家事
- 寝返りをうつとき(夜間痛で目が覚めることも)
2. 夜間の痛み・睡眠障害
炎症が強い時期は夜中にズキズキ痛んで眠れないことが多いです。特に、寝返りや横向き寝で圧がかかると激痛になります。
➡️ 睡眠不足 → 体の疲労 → 回復の遅れ、という悪循環に。
3. 動かさないことによる悪化
痛みがあるからといって腕を動かさないでいると、関節包がさらに縮んで「凍結肩(フローズンショルダー)」になります。 結果として、数か月~1年以上、腕が上がらない状態が続くことも。
4. 心理的・社会的な困りごと
- 痛みで家事や趣味ができなくなる
- 着替えに時間がかかる
- 利き腕が動かないと仕事にも支障
- 「ずっと治らないのでは」と不安・ストレスが強くなる
4. 四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)は安静にした方がいい?動かした方がいい?

四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)は結局安静にしていた方が良いのか、動かしていった方が良いのか?どっちなんだい!!
- 急性期は「無理せず安静」
- 慢性期〜回復期は「少しずつ動かす」
1. 急性期(発症から1〜2か月くらい)
特徴
- 何もしなくても痛い(安静時痛・夜間痛)
- 動かすとズキッと鋭く痛む
- 炎症が強い時期
この時期の対応
- 無理に動かさないことが大切です。
- 炎症が強い状態で動かすと、かえって悪化します。
- 安静にしながら、痛みを和らげるケアを優先します。
例:
- 温めすぎない(炎症期は冷やす方が良い)
- 軽く腕を支えるようにして姿勢を楽にする
- 医師の指示で消炎鎮痛剤や湿布などを使用
2. 慢性期(2〜6か月くらい)
特徴
- 炎症は落ち着くが、肩が固まって動かしにくい
- 痛みは少しマシだが、動かすとツッパリ感や鈍い痛み
この時期の対応
- ここからは動かすことが大事です。
- 放置すると関節包が縮んで「凍結肩」になります。
- 無理のない範囲で**ストレッチやリハビリ**を開始します。
例:
- 壁を伝って指を歩かせるように上げる「壁歩き運動」
- 肘を曲げて前後に軽く揺らす「コッドマン体操」
- 温めてから動かすと痛みがやわらぐ
—
3. 回復期(6か月〜1年)
特徴
- 痛みが少なくなり、徐々に動きが戻る
- 動かすと軽い張りや違和感が残る
この時期の対応
- 継続的に動かすことで可動域を完全に戻す
- 肩・背中・腕の筋力も一緒に回復させる
ちなみに放置すると…
痛みは数年で自然に落ち着くこともありますが、
可動域が戻らないまま固まる(凍結肩)リスクがあります。
そのため、「痛みが少し落ち着いたら動かす」が理想です。
5. 四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)まとめ

肩関節周囲炎は、痛みが強い時期は安静に、痛みが落ち着いてきたら少しずつ動かすことが大切です。
しかし、どのくらい動かしていいのか、どんな運動をすればいいのか、自分では判断が難しいことも多いですよね。
筋トレデイサービス ビーボ では、機能訓練指導員の指導のもと、肩の状態に合わせた安全な運動に取り組んでいただいております。
無理のない範囲で動かしながら、痛みの軽減や可動域の回復を目指しましょう。
「最近、肩が上がらない」「夜中に肩がズキズキする」などの症状がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
ビーボでの体験を通して、肩を安心して動かせる感覚を取り戻してみませんか?
後編は運動するタイミングやどんな運動をしたら良いか、日常生活で気をつけることなどを書きたいと思います!お楽しみに!!
ビーボでは専門の知識を持った機能訓練指導員が2名おりますので、それぞれの利用者様のニーズにお答えできると思います。是非体験してみてください!肩関節周囲炎の方だけでなく、パーキンソン病や変形性膝関節症、高次脳機能障害、認知症の方もトレーニングされています!ビーボ一同お待ちしております!!