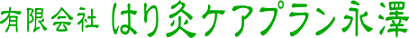パーキンソン病に罹患したら何に困る?どんなリハビリがある?

パーキンソン病やパーキンソン症候群に罹患された方やそのご家族の方は、これから日常生活の中でどんなことに困ったり、悩んだりするのか、どんな問題にぶつかるのか不安に思っているのではないでしょうか?今回のブログを読んでいただくと、パーキンソン病の方がどのようなことで困っていて、その症状を軽減したり、進行を遅らせるためには何をしたら良いかがわかります。
パーキンソン病の症状とは
振戦(ふるえ)、動作緩慢、筋強剛、姿勢保持障害(転倒しやすいこと)を主な運動症状とする、50歳以上で起こることが多い病気です。
運動症状は振戦が最も多く、次に動作の拙劣さが続く。姿勢反射障害やすくみ足で発症することはない。症状の左右差があることが多い。
歩行は前傾前屈姿勢で、前後にも横にも歩幅が狭く、歩行速度は遅くなる。進行例では、進行時に足が地面に張り付いて離れなくなり、いわゆるすくみ足がみられる。方向転換するときや狭い場所を通過する時に障害が目立つ。
また、意欲低下、認知機能障害、幻視、幻覚、妄想などの多彩な非運動症状が認められる。
このほか睡眠障害(昼間の過眠、REM睡眠行動異常など)、自律神経障害(便秘、頻尿、発汗異常、起立性低血圧)、嗅覚の低下、痛みやしびれ)、浮腫など様々な症状を伴うことがある。

パーキンソン病で困ることは
1. 運動障害 筋肉のこわばり、ゆっくりした動き、バランスの悪さなどが日常生活や外出時に困難を生じる。また転倒しやすく長期の入院に繋がり急激な体力の低下に繋がってしまう。
2. 日常生活の制約 身の回りの日常生活動作において、服の着脱、食事の準備、入浴などが難しくなる場合がある。
3. 認知機能の低下 注意力、判断力、記憶力などの認知機能の低下が進行することがあり、日常生活や社会生活に影響を及ぼす。
4. 声の問題 発声が小さくなったり、声が震えたりすることで、他者とのコミュニケーションに支障をきたすことがある。
5. 睡眠障害 睡眠中に体の動きが多くなり、眠りが浅くなったり、夜間に起きやすくなることがある。
6. 精神的な問題 ディスフィギュアメント(顔の筋肉のけいれんによる表情の変化)、抑うつ、不安などが発生することがある。
7. 食欲不振や嚥下障害 食事量が減少したり、食べることが困難になることがある。
8. 社会的孤立 症状や疾患により、友人や家族との交流が減少し、孤立感を感じることがある。

パーキンソン病のリハビリとは
1. 運動療法 物理療法士や作業療法士が指導する運動プログラム。筋力トレーニング、バランス改善、歩行訓練などが含まれる。
2. 言語療法 言語や嚥下の問題を改善するための療法。言語壁や嚥下障害に対処する。
3. 認知療法 認知機能の低下を遅らせるためのトレーニング。記憶力や注意力を向上させるための課題が含まれることがある。
4. 日常生活動作の訓練 日常生活で必要な動作(服の着脱、食事の準備など)を改善するための訓練。
5. 音楽療法 音楽を使ったリズミカルな運動や歌唱を通じて運動機能や認知機能を改善する。
これらのリハビリテーションプログラムは、症状の進行を遅らせたり、日常生活の質を向上させたりする効果が期待されています。ただし、個々の状況に応じて適切なプログラムが選択される必要があります。

パーキンソン病のリハビリの効果
パーキンソン病のリハビリテーションは症状の緩和や機能の維持改善を目指すために重要です。適切なリハビリプログラムは以下のような効果が期待されます
1. 運動機能の改善 運動療法や理学療法は筋力や柔軟性を改善し、運動能力や日常生活の動作に対する困難を軽減するのに役立ちます。
2. バランスの改善 バランスを改善するトレーニングは、転倒リスクを減らし、安全性を高めるのに役立ちます。
3. 認知機能の維持 認知療法や認知行動療法は認知機能の維持や改善を支援し、日常生活の制約を軽減します。
4. 日常生活の支援 作業療法は、日常生活の動作や環境への適応を支援し、自立した生活を維持するのに役立ちます。
リハビリテーションの効果は個人差がありますが、定期的なプログラムの実施や継続的な取り組みが重要です。また、医師やリハビリテーション専門家と連携して、適切なリハビリテーションプランを立てることが大切です。

まとめ
リハビリの主な目的は「症状を軽減すること」と「症状の進行を遅らせること」です。
例えば、無動(動作緩慢)は外部からの刺激(視覚や音のリズム)で軽減します。すくみ足や小刻み歩行も同じです。筋固縮は、症状にあった運動やリラックスすることで軽減します。パーキンソン病の場合のリハビリの主目標は、症状の進行を予防しながら日常生活において困難になってしまった動作を再び行いやすくしていくことです。そのためには専門的な知識を持った指導者の元で、できるだけ体を動かす機会を作ることが必要であると思います。
ビーボでは機能訓練指導員が多くのパーキンソン病の利用者の個別機能訓練に携わっております。経験豊富な指導員と一緒に体を動かして、できるだけ長い期間、日常生活を快適に過ごしていきませんか?パーキンソン病だけでなく、脊柱菅狭窄症や変形性膝関節症、高次脳機能障害、認知症の方もトレーニングされています!ビーボ一同お待ちしております!!